走る 一般道 Ⅰ

~ 新任ドラバー向け指導方法 Ⅰ ~
一般道路▶同交差点▶生活道路▶同交差点▶高速道路

業務開始前運転の社員に何を教えて良いか?… 再教育をしようと考えたとき…
どのように運転について教育・指導をすれば良いのでしょうか?
その一つが、原点回帰講習の内容(車とは、人間とは等)です。
もう一つは、車の運転を考えたとき、車は道路を走行しますので、道路を走ることに焦点をあてて順次説明していくのもひとつと考えます。
今回、道路を走るということに焦点をあてて、一般道路▶同交差点▶生活道路▶同交差点▶高速道路の順に安全に走行するために、ヒヤリハット・事故事例等を基に説明します。
▌道路について

道路について、ドライバーとして知っておくべき内容を説明します。
道路交通法の「道路」とは、
道路交通法第2条第1項では、以下の3つに該当する場合を道路としている。
・道路法第2条第1項に規定する道路(いわゆる公道)
・道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
(もっぱら自動車の交通の用に供することを目的として設けられ
た道で道路法による道路以外のもの)
・一般交通の用に供するその他の場所

▌道路とは(国土交通省)
(1)道路法上の道路
・道路法第三条 道路の種類で次条各号に掲げるものをいう
道路の種類
①高速自動車国道
②一般国道
③都道府県道
④市町村道

私どもが車を運転するうえで、頻繁に走行し、言葉としてよく使う
❶高速道路 ❷一般道路 ❸生活道路(2026年9月の施行予定)について走行する際、意識し注意すべき点に説明します。
まず、上記❷の一般道路の走行関係から説明します。



国道等道路を走行するさいは、センターライン(中央線)の有無が判断材料の一つです。
〇中央線(センターライン)のある道路▶ 車道が5.5m以上 ▶片側一車線が2.75m以上ある
〇中央線(センターライン)のない道路▶ 車道が5.5m未満 ▶生活道路(2026年9月の施予定)
一般道路での速度は、最高速度の標識(指定速度)などがある区間を除き、道路交通法施行令の第11条(最高速度)で規定されている速度(法定速度)です。
「(前文省略)自動車にあっては60km/h、原付にあっては30km/hとする」と規定されています。
規制の目的
と現状

車道とは自動車などの車両が通行するために設けられた空間
道路交通法での車道は、車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。(道路交通法第二条三)
車道は下記写真のように車線により区分され、道路の種類、交通量、設計速度などから車線の幅員は決定されます。

※ 自車車両の寸法と、基本数値を知っておれば、あらゆる道路環境内での物を見る判断ができます。
例えば、まずセンターラインの有無によって判断ができます。
▶センターラインがあれば、その車道は、5.5m以上
▶センターラインがなければ、その車道は5.5m未満
に区分され、下記写真のような判断基準ができます。

図例
中央線
▶


▌法定の追い越し禁止区間
道路交通法第30条では、次のような場所を
追い越し禁止区間としています。
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近
・勾配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
・交差点とその手前から30m以内の場所
(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切
・横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m
以内の場所
▌指定の追い越し禁止区間(右図)
公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めて指定した場所


●車道外側線と路側帯の違い
道路に歩道があるかどうかです。
歩道があれば、車道外側線です。
▌車道外側線は、
車道上の車両進路方向に対して左側に引か
れた白の実線で、路側帯や路肩を車道と
区画する区画線です。

▌路側帯は、
歩行者の通行のために車道に設けられた帯状の区画で、歩行者の安全を守る役割を果たしてい
ます。
▼『路肩』と『路側帯』
『路肩』は道路構造令、『路側帯』は道路交通法において明確に定義されています。
【路肩】(道路構造令第2条12)
道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は
自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分。
【路側帯】(道路交通法第2条3の4)
歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又
は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路
標示によって区画されたもの。
▌路側帯と路肩の違い
逆に、道路構造令に『路側帯』、道路交通法に『路肩』という定義はありません。
そのため、『路肩』と『路側帯』の違いをまとめると、下記のようなものとなります。
(1)定義されている法律が異なる
(2)歩道がある(側の)道路に路側帯はない
(3)歩道がない道路で道路標示によって区画されたものを道路交通法では路側帯という
ただし、(3)については道路構造令では『路肩』と定義もされます。そのため高速道路の車線
の外側のスペースは『路肩』であり『路側帯』でもあるということです。
実際に、道路構造令の規定を解説する国土交通省の資料では『路肩』、警視庁が所管する道路交
通法では『路側帯』と表記されています。
また、高速道路で「路肩を走ってはいけない」という交通ルールは、道路交通法の路側帯の通行
区分違反となるためです。【YouTuber動画 高速道路の路肩走行を見る】

車道外側線
歩道がある場合、車が通行する部分を車道という表現 になります。
車道外側線と歩道の間も 車道として扱われるので、左折する時には
中に入り二輪 車の巻き込みを防止しまし ょう!
ただし、車道外側線が狭い時は入ら なくても大丈夫です!

道路交通法第17条1項(通行区分)
車両は、歩道と歩道又は路側帯と区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。 ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、歩道を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない
道路交通法では導流帯に入ること自体は禁止されておらず、罰則もない。
ただし、各都道府県の公安委員会が独自に定めた事項によってはこの限りではありません。
参考-宮城県内では同県公安委員会が定めた道路交通規則第14条 に基づき、導流帯を含む道路標示の上をみだりに運転することを禁じている。

導流帯に類似したものに、白の斜線のゼブラ表示を黄の縁線で囲んだ「立入り禁止部分」の規制標示がある。この標示は、道路交通法第17条第6項で定められた車両の通行の用に供しない部分であることを表示するもので、立ち入りが禁止され、違反に対する罰則も定められています。
右の図の様な場所は「停止禁止部分」で、路面電車の進行の妨げになる場所や、警察署や消防署の前などで見かけることが多い規制標示です。
黄色の線で囲まれていませんので進入禁止ではありませんが、信号待ちや渋滞時にこの停止禁止部分の内側で停車しないように注意する必要があります。

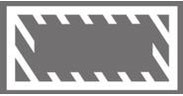
▌導流帯での事故過失割合
進路変更車とゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故 (ソニー損保)
同一方向に進行中に、進路変更を行った四輪車と後続の直進四輪車が衝突した場合の基本過失割合はA:30%、B:70%です。
しかし、ゼブラゾーンを走行している場合は過失の修正が発生する場合があります。車両の運転者等の意識として、ゼブラゾーンにみだりに進入すべきではないと考えているのが一般的であるため、Aに対して10~20%の過失が上乗せされることがあります。なお、道路交通法ではゼブラゾーンに入ることは禁止されておらず、ゼブラゾーンを走行したからといって罰則もありません。

右の表は、某連合協会のヒヤリハットデータを集計分析したものです。
一般道走行時で最も多いのが、
❶割込み・車線変更38件
❷とび出し23件
❸前車急減速・停止18件
確認不足18件
となっています。
また、下の表の「保険スクエアbang! 自動車保険」が行った「交通事故とヒヤリハットに関する意識調査」でも、
❶歩行者・自転車の飛出し
❷他車の強引な追い越し割込み
❸自転車、バイクの強引なすり抜け
となっています。
▼各ヒヤリハットデータから防止策を考えて
みます。
ヒャリハットの内容では、どのような場所でのヒヤリハットなのか判断しにくいですが、写真の(横断歩道)で人や 自転車飛び出してきたと、感じているなら間違いです。
では、どのような考え方で走行すればよいのか考えた見ましょう。
まず、信号機のない横断歩道についてです。


横断歩道を渡っている歩行者がいる場合は、
一時停止し、歩行者に道を譲らなければいけません。
ですから【横断歩道は歩行者優先】
なのです。
事故の基本過失割合は、自動車100%:歩行者0%となります。(ソニー損保)

しかし現実はどうでしょうか?
皆さんは、横断歩道に歩行者がいる場合停止していますか? 半数程度しか止まれていません。
参考となるデータが右のJAFが調査したデータに基づくグラフが右のグラフです。(全国平均の推移)


▼参考
下記内容は、歩行者優先の交通事故のない社会を目指すリース会社キムラユニティー(株)の8つの行動指針です。
横断歩道での事故を起こさない為にも実践してみてください。
8つの行動目標
① 1つ目の◇マークを見たらアクセルオフ
② 2つ目の◇マークを見たら減速
③ 横断歩道付近に歩行者がいたら一時停止
④ 歩行者がいるかいないかわからないときは止ま
れる速度で進行
⑤ 横断歩道手前で車両を追い抜く時は一時停止
⑥ 歩行者とは距離を空けて進行
⑦ 後続車から追突されないように早めのブレーキ
⑧ 発進時は歩行者等、周囲確認の徹底
次に、戸惑うのは自転車を見た場合です。

▼自転車の横断(自転車横断帯有無別)
▌横断歩道に「自転車横断帯」がある場合
●「自転車横断帯」がある場合は自転車が優先権を持つ
~ クルマやバイクは自転車の通行を妨げてはいけません。
●自転車は軽車両であるため、”横断歩道”での横断歩行者に対する優先権はない。
▌横断歩道に「自転車横断帯」がない場合

写真①のように「自転車から降りて横断待ちをしている場合」サドルに腰をかけておらず、両足が地面についている場合は、軽車両ではなく「歩行者扱い」となります。
しかし、写真②のようにサドルに跨がって乗っている場合は歩行者扱いとはなりません。が、
横断歩道ではない写真③のように道路横断中の自転車と車の事故では、
~ 基本過失割合は、 自動車70%自転車30% となっています。
写真②のような場合、法律上はそのまま通過しても問題ないケースであっても、上記事故過失割合等から考えても横断歩道に自転車がいる場合、止まるのがベストです。



ヒヤリハット520件中、一般道直進中は130件発生し、多いのは、【割込み・進路変更38件 次に【飛出し23件】となっています。
飛出しの内容をみますと、右表のとおり歩行者9件、自転車7件、自動車6件となっています。
▌自動車の飛出しは6件中、施設からの飛出しが5件で80%占め、
場所はコンビニやホームセンターからとなっています。
直進側の車は、ハンドル回避や急ブレーキで事故を回避しています。


◎ 施設前を通過する際は、いつ飛びしてくるかもしれないので、通過する前に 駐車場等の状況を確認し、対応できるように速度を落として進行してください。
※ 施設出入り時事故の基本過失割合は下記の図のとおりです。



思い込みヒヤリハットと事故事例から
▶ 右上の写真①は、コンビニの二箇所出入り口から同時ぐらいに出た車両のDR映像で、DR側のドライバーは、トラックは右折出と思って左折したが、実は左折出をしておりヒャリハット事例となったもの。
▶右の写真②は、前車が左折入場するものと思い込み速度を落とさず直進したところ、入場できず停止したトラックに衝突したDR映像です。
次は、一般道走行時での追突について考えてみます。
一般道路での渋滞は、事故や車線規制、ゴルデンウイークやイベントなど、さばききれないほどの車両集中によって発生します。
渋滞時、特に気をつけることは、
との調査結果もあることです。(阪神高速道路交通統計データ)
渋滞時の事故は、車間距離が短いことによる追突事故や強引な車線変更による接触事故が多発しています。

渋滞時の運転で気を付けること
1.車間距離をとる~渋滞時の追突事故が多い。
2.車線変更をむやみにしない~目的の無い車線変更は控え最低限に抑える。
3.わき見運転をしない~ながらスマホは絶対しない。
4.進み出しても油断しない~速度が回復しても、急加速しない心がけが必要
5.集中力を切らさない~渋滞は速度の変化や頻繁な停止の判断を迫られる。
6.ブレーキ、アクセルワークを意識する~安全走行するためにも
ブレーキ、アクセルのペダルワークを意識した運転が必要です。

安全運転管理支援内容については、電話か下記ボタンよりお問い合わせください。
香里自動車教習所 安全運転管理支援チーム ℡ 072-831-0668 fax 072-834-0067

追突事故はどうして起きるのか?
の 分析内容では、イタルダ・インフォメーションno43では、追突事故の約60%が単路で発生し、そのほとんどは信号のない場所で発生しています。
平成13年の追突事故は204,324件あり、乗用車対乗用車の組み合わせが約66%と最も多く、その次は乗用車と小型トラックの組み合わせで約24%となっています。
人身損傷程度は、ほとんどの場合、追突側は無傷、追突された側は大半が軽傷となっています。
追突でのトライバーのエラーは「背景エラー」と「直接エラー」で391件あります。
両者で多いのは、直接エラーが約70%を占め、直接エラー内容は認知エラーが80%を占めています。
また、運転者の油断を誘う「背景エラー」は、判断・予測エラーが約80%占めています。
認知エラーの大半は、先行車や駐停止・事故車両を「見なかった 」「見えなかった」と回答し、判断・予測エラーは、「減速しない」「車間距離は妥当」の順に多く、その背景は「思い込み・慣れ」「普段の通り」が多くなっています。
【車は、急に止まらない】ことを意識してください。
私ども、支援チームは企業講習で基本を見直す原点回帰講習を実施していますが、その中で感じることは、受講者の大半が停止距離を短い距離で停止できると感じていることです。
車の運転は、ドライバー(人間)の【認知】【判断】【操作】で行っており、これを実践するには必ず時間が必要になります。
すなわち車を動かしながらの【認知】【判断】【操作】は、速度に対応した停止距離が存在するのです。
では、あなたの反応時間を検証しましょう。
まず、下の表予測蘭に5Kmと40Km時の予測した停止距離を記入してください。

次にスマホで下のQRコードを読み込みます。
まず、左の説明動画を観てから右側のQRコードを読み込ん
で、検証してください。


検証した結果はどうでしたか? この時間があなたの【認知】【判断】【操作】にかかる時間です。今回は指での操作ですが実際はブレーキを踏むのは足での操作になり、もう少し時間がかかると思います。
速度5Kmの場合では、1m前後の停止距離があり、速度40Kmでは16m前後の停止距離になると思います。
この検証でも分かりますように車は急に止まらないのです。そのことを意識して前車との車間距離を空けるようにしてください。
では、どれぐらい車間距離をとればいいのでしょうか?
▌渋滞時や信号待ち等停止中の車間距離は、
車1台分(4~5m)空けてください。
特にトラックの場合、狭くなる傾向が
あります。
~ ①一度、運転するトラックで普通車
の後ろに日頃の車間距離で止めてみ
てください。
②次に乗用車に乗って、バックミラー、
サイドミラーを見てください!
●威圧に感じるか? 感じないか?
▌車間距離をとる理由
◇前車に威圧を与えない。
➤煽り運転の要因になる恐れあり
◇発進時の追突防止➤時間と距離の確保
◇左右回避時の安心感
➤前車が動かなくなった場合など
◇多重追突防止


「前車との車間距離を空けると割り込まれる!」と考えている方へ
4~5m空けていても入る車は、1台です。トラックの場合会社名が記入してあるならなおさらです。あなたも渋滞時に車線変更等で入れてもらう場合があることを考えれば、入れてあげてください。
▌渋滞時、発進する際は、信号や遠くの
状況確認の前に目の前の確認を!
~車間距離が狭いと、玉突き事故や多重追突になる場合があります。
▶追突事故の基本過失割合は右図のとおりで、玉突き追突事故か?多重追突事故(2つの事故)か?で内容が変わります。
道路交通法26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
直進走行時追突事故内容
●片側4車線の現場を走行中、前方に車線変更してきたトレーラーの直後の減速に対応出来ず右車線に回避しようとしたが当車の左ミラーを先方のコンテナ右後方部分に接触させた(車間距離、入れてあげる気持ち)
●走行中、助手席に置いてあった書類が気になり目線をはずした為に右折しようとしていた相手車両に気付くのが遅れ追突した(脇見)
●走行中に渋滞の為停車している車両の発見が遅れ追突した(車間距離)
●キャビン内で送り状と携帯マップを確認中、車両が前方に動き出しフットブレーキを踏もうとしたが間に合わず前方に駐車していた乗用車に追突(サイドブレーキ不備)

他車運送会社渋滞中の追突内容
🚚 渋滞気味の中を走行中考え事をしてしまい、先行車輌が速度を落としたことに気づかず、後部より追突(前車の動静確認不足)
🚚 渋滞道路を10km~20kmまで落とし走行。直前車両のその前方車両が交差点内で停止した為、直前車両が停止した事に気付くのが遅れ追突(前車の動静確認不足)
渋滞中追突事故事例(食品会社)
🚗 渋滞中の直線道路で停止時にブレーキを踏んでいたつもりが踏み込みが甘くなりクリープ現象で前車に追突した。(停車時のブレーキ操作)
🚗 直線道路を直線走行中、前方が渋滞し停車。 前方の交通が流れ出し前車も発進するだろうと考えて発進。しかし、前方車両が発進せず、後方より追突(判断誤り)









